日本の木綿発祥の地として知られる三河地方。そこで織られた三河木綿は、江戸時代から質の高い木綿産地として全国に知られました。幸田町郷土資料館では、この伝統的な織物文化の歩みをたどる企画展示が開催されます。手機の技術から機械紡績の発展まで、町の近代化を支えた繊維業の歴史を通じて、木綿織物が現代に伝える意義を探る貴重な機会となりそうです。
- 崑崙人漂着から始まった木綿の歴史
- 手機から機械へ、技術革新の軌跡
- 徳川家康を支えた名門の系譜
- 島原藩主として西国を監視した深溝松平家
- 開催情報
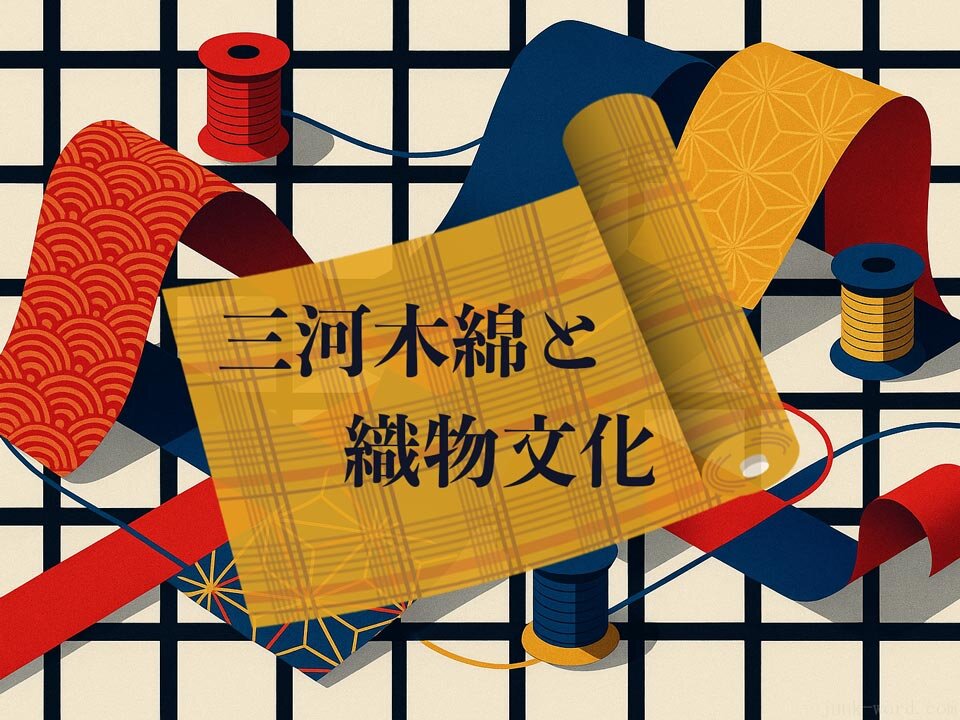
日本木綿発祥の地に残る伝承
崑崙人漂着から始まった木綿の歴史
三河地方が日本の木綿発祥の地とされる背景には、古い文献に記された伝説があります。延暦年間(8世紀末)の『日本後記』や『類聚国史』によると、崑崙人(こんろんじん:インド人とされるが諸説あり)が愛知県幡豆郡福地村(現在の西尾市)に綿種を持って漂着したとされています。西尾市天竹町には綿神を祀る天竹神社があり、この伝承を今に伝えています。
この漂着の記録は史料で確認されていますが、実際の綿栽培の定着にはその後長い時間を要しました。国産木綿が文献に登場するのは永正7年(1510年)の興福寺大乗院の文書で、「三川木綿」として年貢に使われた記録が残っています。この頃から三河地方で本格的な綿業が始まったと考えられており、江戸時代には「三白木綿(さんぱくもめん)」として河内木綿と並ぶ全国有数の産地として発展していきました。
手機から機械へ、技術革新の軌跡
三河木綿の特徴は、その製造技術の変遷にも表れています。江戸時代当初は農家の副業として手機(てばた)による織りが中心でした。手機とは人力で操作する織機のことで、経糸(たていと)に緯糸(よこいと)を交互に組み合わせて布を織り上げる道具です。この伝統的な織りは「ウチオリ(内織・家織ち)」と呼ばれ、各家庭で衣服や日用品を自給するために続けられていました。
明治時代に入ると、西洋の機械技術が導入され、三河地方の木綿業は大きな転換期を迎えます。ガラ紡(ガラガラと音がすることから名付けられた国産の綿紡績機)や洋綿紡績糸の技術により生産性が飛躍的に向上しました。これにより色糸を用いた多様な三河縞の織物が可能となり、縞柄や格子柄の美しい織物が全国に広まることとなったのです。
手機の技術は機械化の波を受けながらも完全に失われることなく、現在も三河木綿織の保存会組織によって受け継がれています。伝統的な手紡ぎや草木染の技法は、現代の私たちにものづくりの原点を教えてくれる貴重な文化遺産なのです。
深溝松平家と幸田町の歴史的背景
徳川家康を支えた名門の系譜
三河木綿が発展した幸田町は、深溝松平家(ふこうずまつだいらけ)発祥の地としても知られています。深溝松平家は江戸時代に「十八松平」と称された松平氏の一家で、深溝を領地としたことからこの名で呼ばれるようになりました。初代松平忠定が深溝の地を本拠としたことに始まり、四代家忠まで深溝を治めました。
深溝松平家では五代忠利以降、歴代当主は死没地に関わらず、必ず発祥の地である深溝の菩提寺・瑞雲山本光寺(ずいうんざんほんこうじ)に遺骸を埋葬するという方針を貫きました。江戸時代の大名家でこのような埋葬方法を取った例は全国的にも珍しく、現在は国指定史跡として保護されています。この背景には、故郷への深い愛着と家系の誇りがあったと考えられています。
島原藩主として西国を監視した深溝松平家
深溝松平家は、六代忠房の代に肥前島原藩主となり、幕末に至るまで西国大名の監視という重要な役割を担いました。島原は長崎に近く、江戸時代後期には外国船の往来が活発化したことから、海岸防備の強化が求められる戦略上の要地となっていました。深溝松平家は幕府の命を受け、兵を動員して国防の任にあたりました。
1843年には、島原藩の今村刑場で、西洋医学の普及を目的とした罪人の解剖が実施されました。このときの解剖図は、島原市の文化財として「肥前島原松平文庫」に保管されています。こうした先進的な取り組みからも、深溝松平家が時代の変化に敏感に対応しようとしていた姿勢がうかがえます。
深溝松平家十八代忠和は、水戸藩主徳川斉昭の子で、将軍慶喜の弟でした。幕末の混乱期に慎重な行動を取りながらも時代の変化に対応し、版籍奉還後は島原藩知事、さらに子爵位も授けられています。
開催情報
| 展示名 | 三河木綿ことはじめ-伝承技術の手機と縞- |
|---|---|
| 主催 | 幸田町郷土資料館 |
| 会期 | 令和7年6月1日(日)~11月3日(月・祝) |
| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |
| 入館料 | 記載なし(郷土資料館にお問い合わせください) |
| 休館日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日) ※期間中、木曜日は通常開館 |
三河木綿と深溝松平家のまとめ
- 延暦18年崑崙人漂着伝説が三河木綿発祥の起源
- 永正7年「三川木綿」が文献初登場
- 江戸時代「三白木綿」として全国ブランド化
- 手機による「ウチオリ」で各家庭が衣服を自給
- 明治時代ガラ紡導入で生産性が飛躍的向上
- 色糸使用で多様な三河縞の織物が誕生
- 伝統技術は現在も保存会組織が継承
- 深溝松平家は「十八松平」の名門一家
- 歴代当主を故郷深溝に埋葬する独特方針
- 六代忠房から島原藩主として西国を監視
- 1843年西洋医学普及で解剖を実施
- 十八代忠和は将軍慶喜の弟という血筋

