福島県白河市の小峰城歴史館で9月13日より開催される特別企画展「松平定信の文化力」は、寛政の改革で知られる政治家の意外な一面に焦点を当てた興味深い展示です。定信自筆の書画、詠歌や随筆などの文芸作品、『集古十種』の編さんや絵巻物の模写といった文化財保護・調査研究に関する資料を通して、厳格な改革者として記憶される定信の多彩な文化的業績を紹介します。生涯を通じて文化活動に取り組んだ定信の、縦横無尽の「文化力」を感じられる展示となっています。
- 寛政の改革の光と影
- 評価の変遷と現代の見方
- 文化人としての松平定信
- 南北朝時代の築城:小峰城を築いた結城氏の系譜
- 近世城郭への大改修
- 東北の戦略拠点として
- 開催情報
- 2025年度開催中の江戸時代関連展示
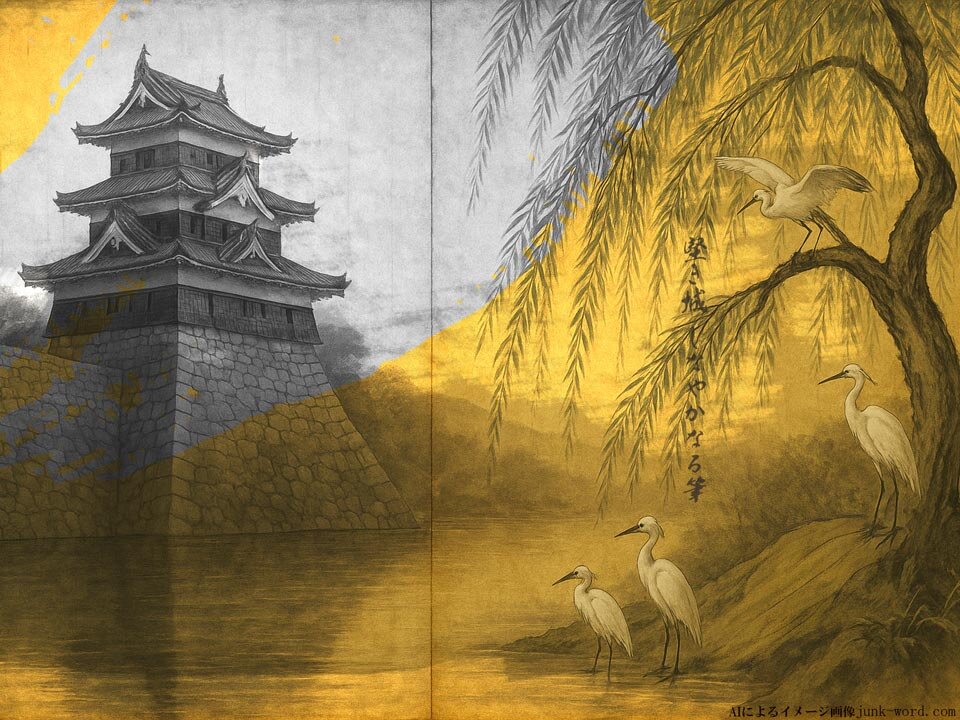
寛政の改革は本当に失敗だったのか・良い点と悪い点を検証
寛政の改革の光と影
江戸時代、陸奥国白河藩主で老中首座・松平定信によって断行された「寛政の改革」。
これは享保・天保の改革と並ぶ江戸幕府の三大改革の一つであり、田沼意次(たぬまおきつぐ)の政治からの劇的な転換点として位置づけられています。その理想主義的な政策は、幕政に一時の安定をもたらした一方で、社会に深刻な停滞感も生み出しました。寛政の改革が持つ光と影を解説します。
寛政の改革が目指した最大の目標は、逼迫した幕府財政の再建と、天明の大飢饉を経て混乱した社会秩序の回復でした。
松平定信は、祖父である8代将軍・徳川吉宗の享保の改革を理想とし、徹底した緊縮財政に着手します。大奥の経費削減をはじめ、幕府のあらゆる支出を切り詰め、財政の引き締めを進めます。これは改革の明確な成果と言えるでしょう。
厳格すぎる統制と思想への介入
しかし、定信の清廉潔白さと理想主義は、現実社会との間に大きな乖離を生み出します。その弊害は、主に三つの側面に現れました。
第一に、厳格すぎる倹約令と風俗統制です。武士や庶民の服装から髪型、私的な会食に至るまで細かく規制し、町人文化の担い手であった洒落本や黄表紙などの出版物を厳しく弾圧しました。これにより山東京伝(さんとうきょうでん)らの作家が処罰されるなど、町人文化の自由闊達な気風は失われ、社会全体が息苦しい空気に覆われることになったのです。
第二に、思想・学問への介入があげられます。定信は、幕府の教学の柱を朱子学に一本化する「寛政異学の禁」を発令しました。これにより、幕府の学問所における朱子学以外の講義が禁じられ、学問の多様性が損なわれました。これは、幕藩体制のイデオロギーを強化する狙いがありましたが、自由な思想の発展を阻害する結果を招きました。
第三に、武士救済策がもたらした経済的混乱です。旗本・御家人の困窮を救うため、彼らが札差(武士の俸禄を担保に融資する金融業者)から受けた過去の借金について、利息や元金の一部を免除させる「棄捐令(きえんれい)」を発布しました。これは武士層からは歓迎されましたが、札差に一方的な負担を強いるものであり、大きな打撃を与えました。結果として金融市場の信用は縮小し、武士たちも新たな資金の借入が難しくなるという矛盾した状況を生み出しました。
評価の変遷と現代の見方
近年の研究では、松平定信の改革政策が田沼意次の施策を全面的に否定したものではなく、株仲間や冥加金、公金貸付といった要素を一部継承していたことも明らかになってきました。また、南鐐二朱判についても田沼期に発行されたものが引き続き流通しました。
また、飢饉の教訓から、従来からあった義倉や社倉を活用し、米を備蓄させる「囲い米」の制度を全国的に奨励・徹底しました。これは食糧安全保障の観点から先駆的な取り組みといえ、民生の安定に寄与した側面は高く評価されます。
さらに、江戸の治安維持のために無宿人や軽犯罪者を収容し、労働を課する「人足寄場(にんそくよせば)」を石川島に設置するなど、社会政策にも手腕を発揮しました。
定信の改革は、幕府財政の健全化や社会秩序の回復といった一定の成果を上げたものの、その復古主義的で厳格すぎる手法は、社会の活力や文化の多様性を削いでしまいました。高潔な理想を掲げながらも、時代の変化と人間の機微を汲み取れなかったが故に民心を得られず、短期で終焉を迎えたのです。
寛政の改革は、従来の「田沼政治の否定」という見方を超えて、政策の継続性と社会政策の先進性という新たな意義を持つものでした。定信失脚後も「寛政の遺老」と呼ばれる老中たちによって一部の施策は引き継がれ、囲い米や人足寄場といった取り組みは幕末期まで影響を残したのです。
文化人としての松平定信
松平定信は、寛政の改革を通じて幕府権威の回復や社会の安定を目指しましたが、短期間で辞任に追い込まれました。一方で、文化人としての活動では多数の著作を残し、江戸時代の学問や文化に大きな影響を与えています。
定信は幼い頃から学問に励み、若くして修養書を著すなど、学問への関心が高かったとされます。著作には『花月草紙(かげつそうし)』や『宇下人言(うげのひとこと)』、『国本論(こくほんろん)』などがあり、他にも『修行録(しゅぎょうろく)』といった修養書を残しました。また、『集古十種(しゅうこじっしゅ)』85巻では古画古物の模写約2000点から成る図録集も編纂しています。
注目したいのは、東京国立博物館所蔵の『近世職人尽絵詞(きんせいしょくにんづくしえことば)』との関連です。この絵巻物は、定信が老中退任後に制作発案に関わった可能性が指摘されています。絵に添える詞を寄せたのは、上巻・大田南畝(おおたなんぽ)、中巻・朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)、下巻・山東京伝でした。
山東京伝は、洒落本を執筆したことで手鎖50日(自宅で手錠をかけられたまま50日間謹慎する刑)に処されました。朋誠堂喜三二は、武士でありながら戯作(げさく)を執筆していましたが、寛政の改革による風俗取締りの影響を受けて筆を折ることになりました。また、大田南畝も、処罰こそ免れたものの、改革下で風刺的な狂歌を控えるなど、その活動に影響を受けた一人です。
『近世職人尽絵詞』の制作に定信が関わっていたのであれば、依頼した定信、そしてそれを受けた戯作者たちの双方が、どのような思いでこの仕事に臨んだのか、今も私たちの想像力を掻き立てます。過去の遺恨を超えて、互いの才能を認め合った結果、この作品が生まれたのかもしれません。定信の厳格な政治家としての一面と、深い文化的素養を持つ一面が同居していることを示す、象徴的な出来事です。

あまり知られていませんが、定信は老中に就任する前に、『大名形気(だいみょうかたぎ)』を著したと伝えられています。内容はすでに刊行されていた他の黄表紙作品に類似しており、模倣的な要素も見られることから、定信が町人文化の一端であった黄表紙に関心を寄せていたことがうかがえます。
洒落本や黄表紙を含む戯作は、江戸時代後期に庶民だけでなく武士階級にも広く親しまれた文学でした。当時、出世が望めず時間を持て余した武士にとって、戯作は仲間内で楽しむ格好の知的遊戯でした。古典や故事の知識を必要とするパロディや風刺が盛り込まれており、高い教養を持つ人々にも楽しまれていました。
黄表紙の流行に火をつけた恋川春町(こいかわはるまち)や朋誠堂喜三二といった人気作家も武士の出身です。武士階級が戯作文化の重要な担い手であり読者層でもあった史実から、高い教養を持つ大名であった定信がこれらの書物を読んでいたとしても不自然ではありません。
松平定信は、為政者としては庶民文化を厳しく統制する一方、一個人の知的関心としては、それらを読んで楽しんだり、自ら筆を執ったりする二面性を持っていた人物像が浮かび上がります。
白河藩の居城 小峰城の歴史
南北朝時代の築城:小峰城を築いた結城氏の系譜
小峰城の成立は、『白河風土記』によれば、興国~正平年間(1340~1369)の頃、白河庄を治めていた結城宗広の嫡男・親朝が築いたと伝えられています。当時の城域は、現在の本丸と三の丸北端の丘陵部で、川に臨む細長い丘の上に築かれていました。
結城氏の本拠は小峰城の東方約3キロに位置する白川城でしたが、永正年間(1504~1520)の一族内紛以降、本拠を小峰城に移したと考えられています。その背景には戦略的要因もあったと推測されます。
近世城郭への大改修
天正18年(1590)の豊臣秀吉による奥羽仕置で結城氏は改易となり、その後は会津若松城を本城とする蒲生氏・上杉氏の支城となりました。関ヶ原の戦い後に上杉・蒲生が去り、寛永4年(1627)、10万石余で入封した丹羽長重が小峰城を大改修し、石垣や櫓を備えた本格的な近世城郭へと生まれ変わらせました。
丹羽長重は、織田信長の宿老・丹羽長秀の子で、築城にも関わったことで知られています。現在も残る壮大な石垣は、この時期に約4年の歳月をかけて築かれたもので、本丸・二之丸を総石垣で固め、三之丸でも門周辺部に石垣を用いるなど、梯郭式(ていかくしき)の平山城として大きく姿を変えました。
東北の戦略拠点として
丹羽長重が転封となったあと、小峰城には榊原・本多・松平(奥平)・松平(結城)・松平(久松)・阿部氏が歴代の藩主として入りました。いずれも徳川ゆかりの親藩や譜代大名であり、東北の外様大名を監視できる小峰城は、幕府にとって重要な戦略拠点だったのです。
歴代藩主の中でも、先に述べた松平(久松)定信は、白河藩主時代の経験や実績を背景に、一橋治済ら将軍家の推挙を受けて老中に抜擢され、寛政の改革を断行しました。
その後、戊辰戦争(1868年)で小峰城は激しい戦火により天守(三重櫓)や御殿が焼失しましたが、平成に入ってから本丸三重櫓や前御門などが復元され、往時の姿が甦りました。
小峰城は、南北朝時代の山城として始まり、江戸時代には石垣を備えた近世城郭へと発展し、約530年間(1340年代~1868年)にわたり東北の要衝を守り続けました。近年では東日本大震災で大きな被害を受けましたが、復旧工事を経て石垣や三重櫓が整備され、市民に親しまれる歴史的シンボルとなっています。こうした長い歴史の中でも、藩政改革や寛政の改革へとつながる経験を重ねた松平定信の時代は、小峰城の歩みに特別な意味を与えています。
開催情報
| 展示名 | 白河市合併20周年記念特別企画展「松平定信の文化力―つくり・しらべ・うつし・つたえる―」 |
|---|---|
| 主催 | 小峰城歴史館、白河市 |
| 会期 | 令和7年9月13日(土曜日)~11月9日(日曜日) |
| 開館時間 | 午前9時~午後5時(最終入館は閉館30分前まで) |
| 観覧料 | 大人300円(250円)、小中高校生・障がい者100円(50円)※( )内は20名以上の団体料金 |
| 休館日 | 毎週月曜日(9 月15 日・22 日、10 月13 日、11 月3 日は開館し、9 月16 日(火曜日)・24 日(水曜日)・10 月14 日(火曜日)・11 月4 日(火曜日)は休館) |
江戸時代関連展示
2025年は大河ドラマ「べらぼう」で蔦屋重三郎に注目が集まっていることもあり、全国の美術館・博物館で江戸時代をテーマとした展示が開催されています。特に浮世絵や大奥、江戸の文化に関する展示が充実しており、松平定信が活躍した寛政期の文化的背景をより深く理解できる機会が豊富に用意されています。
2025年度開催中の江戸時代関連展示
| 施設名 | 展示名 | 会期 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 東京国立博物館 平成館 | 特別展「江戸☆大奥」 | 2025年7月19日~9月21日 | 大奥の女性たちの生活と文化を、楊洲周延の錦絵《千代田の大奥》を一挙公開するほか、武家女性の着物やゆかりの品々で紹介する展覧会 |
| 山種美術館 | 特別展「江戸の人気絵師 夢の競演 宗達から写楽、広重まで」 | 2025年8月9日~9月28日 | 江戸時代に活躍した人気絵師の作品が一堂に会する展覧会。東洲斎写楽の役者大首絵、葛飾北斎《冨嶽三十六景》など浮世絵と江戸絵画の名品を展示 |
| 角川武蔵野ミュージアム | 体感型デジタルアート劇場 浮世絵 RE:BORN | 2025年4月26日~2026年1月18日 | 歌麿、写楽、北斎、広重、国芳らの浮世絵の世界を、デジタルアート技術により体感できる没入型展示 |
| 牧之原市史料館 | 常設展示 | 通期開催 | 田沼意次を中心に田沼家ゆかりの工芸品や古文書、歴史資料など200点以上を展示 |
寛政の改革と文化人松平定信のまとめ
- 寛政の改革は大奥経費削減など財政再建に一定の成果を上げた
- 厳格すぎる統制により社会の活力と文化的多様性を削いだ
- 棄捐令は武士を救済したが金融市場に混乱をもたらした
- 人足寄場設置など社会保障政策の先駆的な取り組みを実施
- 田沼政策の一部を継承し発展させた側面もあった
- 松平定信は政治家であると同時に優れた文化人でもあった
- 『集古十種』など多数の文化的業績を残している
- 老中就任前に『大名形気』という小説を執筆していた
- 処罰した戯作者との文化的交流があった可能性が指摘される
- 小峰城は南北朝時代に結城親朝によって築かれた
- 丹羽長重による大改修で近世城郭としての姿が完成した
- 東北の戦略拠点として7家21代の大名が居城とした

