およそ4万年前の最終氷期には、現生人類(ホモ・サピエンス)とネアンデルタール人が一部地域で同時期に存在していたことが化石や遺伝子研究から示されています。その後ネアンデルタール人は化石記録から姿を消し、現生人類のみが現代まで存続しました。国立科学博物館で開催中の特別展「氷河期展」では、日本初公開となる実物の頭骨を通じて、この分岐の時期に迫ります。マンモスやナウマンゾウなど氷河期の巨大動物と人類の関わりを、最新研究を交えて体感できる貴重な機会です。
- ドイツの谷で始まった人類学革命
- 最新技術が明かす高度な文化
- 海を渡ったナウマンゾウの謎
- 人類到達と絶滅の関係
- 開催情報
- 氷河期・旧石器時代の展示
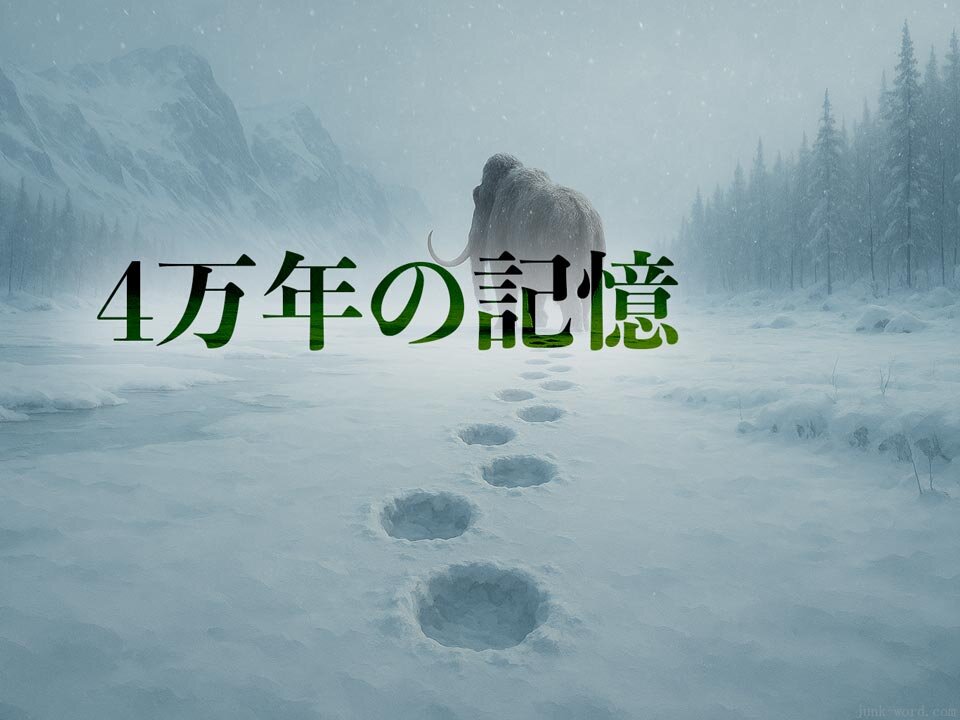
ネアンデルタール人の発見が変えた人類観
ドイツの谷で始まった人類学革命
1856年、ドイツのネアンデル渓谷で石灰岩採掘中に人類化石が見つかり、当初はクマなど動物骨とも考えられましたが、その後の研究で別種の古人類であることが判明し、人類進化研究に大きな転機をもたらしました。
「ネアンデルタール人」という名称は最初期標本が見つかったドイツ・ネアンデル渓谷(独語Tal=谷)に由来します。この発見は、現生人類以外にも別系統の古人類が存在していたことを示す重要な証拠となりました。
ネアンデルタール人は発達した眉の隆起と後傾気味の前額部、がっしりとした骨格と深く幅広い胸郭をもつ個体が多く報告されています。身長は標本により差がありますが概ね150~170cm程度と推定されます。かつては粗野で原始的と見なされがちでしたが、近年の研究でより複雑な行動や文化を示す証拠が増えています。
ネアンデルタール人の発見は、人類が進化の過程で枝分かれしていたという概念を初めて科学的に証明した出来事でした。それまで人類は一直線に進化してきたと考えられていたため、この発見は当時の学界に大きな衝撃を与えました。
最新技術が明かす高度な文化
アンデルタール人はムスティエ文化に代表される石器製作技術を持ち、火や炉跡を利用し、カバノキ樹皮からタール状接着剤を作った例も報告されています。寒冷環境への適応から毛皮などで身体を覆ったとする説や、歯石分析などから薬草利用が考えられる例もあります。また重傷を負った個体(シャニダール1など)が長期生存した化石例から、仲間同士の看護的行動があったとする説もあります。
かつてネアンデルタール人は単純で乱暴な狩猟民とみなされがちでしたが、その後の研究で猛禽類の爪や貝殻を装飾的に用いたとみられる遺物報告など、象徴行動を示唆する事例が増えてきました。スペインのいくつかの洞窟で6万年以上前と測定された赤色顔料痕がネアンデルタール起源かもしれないとする研究もありますが、その解釈については議論が続いています。ディヴィジェベイブ遺跡の穴あき骨を「フルート」とみなす説もありますが、確定的な証拠はありません。
遺伝子解析から、アフリカ以外にルーツをもつ現代人集団のゲノムには概ね1~2%程度のネアンデルタール人由来配列が含まれることが示されています。世界の複数集団を合わせてみると、ネアンデルタール人ゲノムのかなりの部分が断片的に現代人側に残存しているとの報告もあります。
日本列島に渡った氷河期の巨獣たち
海を渡ったナウマンゾウの謎
ナウマンゾウは日本の氷河時代(更新世)を代表するゾウで、化石記録からおおむね約36万年前に出現しました。学名はPalaeoloxodon naumanni(パレオロクソドン・ナウマンニ)で、属名は古いアフリカゾウ系統を意味し、種小名はドイツの地質学者で明治期に日本の地質学草創に大きく貢献したエドムント・ナウマンの名前に由来しています。
ナウマンゾウの化石は北海道でも見つかっており、本州と北海道のあいだで動物が行き来していた可能性が指摘されています。ただし津軽海峡は水深が深く、最終氷期最盛期に世界の海面が現在より約120~130m程度低下していたと推定される時期でも、完全な陸橋が形成されたかどうかははっきりしていません。どのような経路で移動したかについては海氷や島伝い移動など諸説あり、遊泳で横断したと断定できる証拠はありません。
岩手県一関市花泉町(金森遺跡)や長野県上水内郡信濃町の野尻湖畔からはナウマンゾウやヤベオオツノジカやハナイズミモリウシ(ステップバイソン)などの化石と共に旧石器時代の石器や骨器が発見されており、これらの生物は当時の人類の狩猟の対象であったと考えられています。
人類到達と絶滅の関係
ナウマンゾウの最終出現年代は地域差がありますが、約3万年前から約1万5千年前の幅で議論されており、現生人類が拡散した後期旧石器時代と時期が重なる点が注目されています。両者の関係はなお研究途上です。
複数の大型哺乳類が後期更新世に姿を消した背景には、最終氷期以降の環境変動に加え、人類による影響(狩猟・生息域攪乱など)が複合的に関与した可能性が指摘されています。世界的にも、マンモスやケナガサイなど多くの大型動物が人類の拡散時期と重なって絶滅しており、日本列島もこの「第四紀の大量絶滅」の一部として位置づけられています。
一方で、ナウマンゾウと同時代に生息していたニホンジカやイノシシなどの中型哺乳類は現代まで生き残っており、絶滅の要因は動物の体サイズや生態特性とも密接に関連していたと考えられます。大型動物ほど繁殖速度が遅く、環境変化や狩猟圧に対して脆弱であったことが、選択的な絶滅を招いた可能性があります。
開催情報
| 展示名 | 特別展「氷河期展~人類が見た4万年前の世界~」 |
|---|---|
| 主催 | 国立科学博物館、TBS、TBSグロウディア、東京新聞 |
| 会期 | 2025年7月12日(土)~10月13日(月・祝) |
| 開館時間 | 9時~17時(入場は16時30分まで) 夜間開館:8月8日(金)~17日(日)および10月10日(金)~13日(月・祝)は19時閉館 |
| 入場料 | 一般・大学生 2,300円、小・中・高校生 600円 ※未就学児は無料 |
| 休館日 | 7月14日(月)、9月1日(月)、8日(月)、16日(火)、22日(月)、29日(月) |
今回の展示では、日本初公開となるネアンデルタール人とクロマニョン人(ホモ・サピエンス)の実物頭骨を間近で観察できます。展示解説や復元資料も手がかりに、約4万年前の人類像に迫ってみてください。
関連展示
氷河期の人類史や古代日本の考古学に興味を持った方には、日本各地の博物館もおすすめです。日本旧石器研究の端緒として知られる岩宿遺跡や、ナウマンゾウ化石の発掘で著名な野尻湖の博物館では、資料を通じて氷河期の日本を学ぶことができます。
氷河期・旧石器時代の展示
| 施設名 | 展示名 | 会期 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 野尻湖ナウマンゾウ博物館 | 常設展示(氷河時代体験ミニ講座開催中) | 通年開催 | 約4万年前の野尻湖で発掘されたナウマンゾウの実物化石と実物大復元像。氷河期の日本人の狩猟生活を展示 |
| 岩宿博物館 | 常設展示・企画展「縄文時代の始まりと洞窟遺跡」 | 通年開催 | 日本旧石器研究の出発点とされる岩宿遺跡資料を中心に、マンモス展示や岩宿遺跡出土石器などを紹介 |
| 史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館 | 常設展示(旧石器ハテナ館) | 通年開催 | 約2万年前と推定される旧石器時代の住居状遺構(国内最古級)を紹介。定住的活動を示唆する資料を展示 |
ネアンデルタール人とナウマンゾウの謎まとめ
- 1856年ドイツでの発見がネアンデルタール人研究の出発点
- 当初は粗野とされたが高度な文化を持つことが判明
- 石器製作・火の利用・薬草使用など進んだ技術を保有
- 現代人ゲノムの1~2%にネアンデルタール人由来配列が残存
- ナウマンゾウは約36万年前に日本列島に出現
- 野尻湖や花泉町で旧石器時代の石器と共に化石発見
- 絶滅時期は約3万年前から1万5千年前で研究者間で議論
- 人類拡散時期と大型動物絶滅時期の一致が注目される
- 世界的な第四紀大量絶滅の一部として位置づけられる
- 中型動物は生存し大型動物のみ選択的に絶滅
- 日本初公開のネアンデルタール人とクロマニョン人実物頭骨

