那須歴史探訪館で2025年3月28日から開催されている「刊本・摺物ワンダーランド-江戸・明治の出版文化-」展は、江戸時代の出版文化の発展と庶民への広がりを紹介する特別展です。今回の記事では、この展示の見どころと、理解を深めるための基礎知識をご紹介します。現代のSNSやスマホが普及したように、江戸時代にも「情報革命」がありました。
- 江戸時代の出版文化と那須の歴史をつなぐ企画展「刊本・摺物ワンダーランド」
- 企画展の概要:出版文化と地域の歴史が交わる展示
- 江戸時代の出版文化を知る
- 出版文化の誕生と発展
- 「刊本」と「摺物」
- 浮世絵―江戸時代のビジュアルメディア
- 戯作―江戸時代の娯楽小説
- 企画展の見どころ
- 江戸時代の戯作文学と那須の伝説「殺生石」
- 刊本・摺物で見る江戸の庶民文化
- 関連イベント
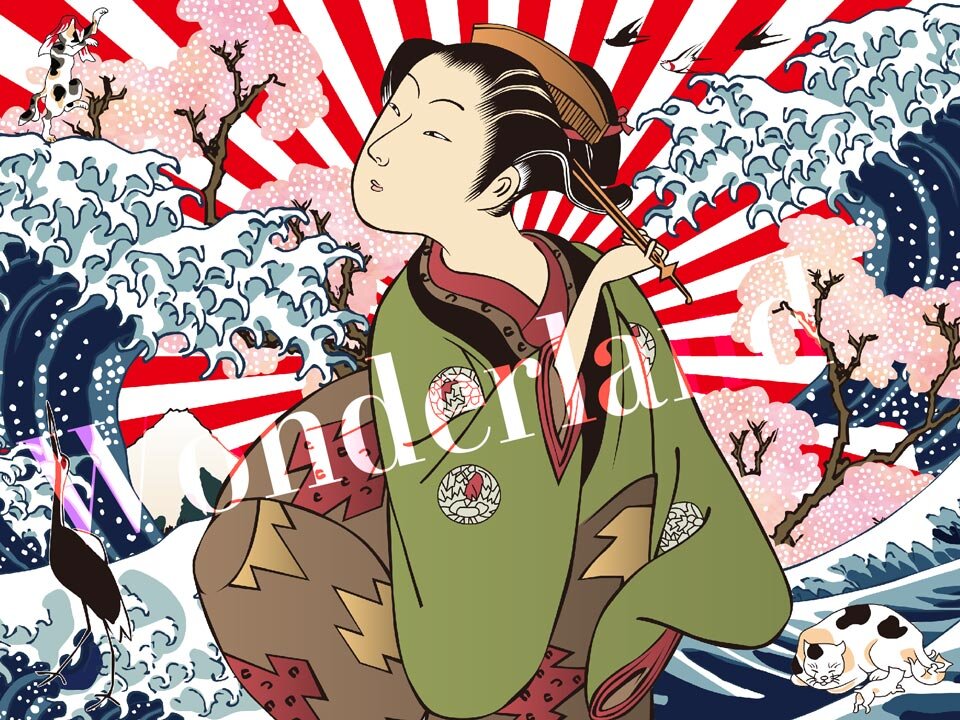
江戸時代の出版文化と那須の歴史をつなぐ企画展「刊本・摺物ワンダーランド」
企画展の概要:出版文化と地域の歴史が交わる展示
那須歴史探訪館では、「刊本・摺物ワンダーランド-江戸・明治の出版文化-」と題した企画展が令和7年3月28日から6月29日まで開催されています。この企画展では、江戸時代から明治にかけての出版文化に焦点を当て、当時の書物や浮世絵などの出版物を展示しています。
特に注目すべきは、那須地域ゆかりの「九尾の狐・殺生石」を題材にした作品の紹介です。高井蘭山の『絵本三国妖婦伝』や曲亭馬琴の『殺生石後日怪談』といった著名な作品が展示されており、江戸時代の出版文化と那須の地域的特色が融合した内容となっています。
また、同時に「生誕150周年 山田英夫~会津・長州・那須を繋ぐ~」というトピック展も開催され、会津藩主・松平容保の三男でありながら長州藩出身の山田顕義の娘と結婚し、那須地域の発展に貢献した山田英夫の足跡を紹介しています。
さらに、那須歴史探訪館所蔵の古文書目録の公開も行われており、地域の歴史研究に貢献する貴重な資料を閲覧することができます。
江戸時代の出版文化を理解するための基礎知識
出版文化の誕生と発展
江戸時代以前の日本では、書物は主に手書きで作られており、一般の人々が手に入れたり読んだりすることは困難でした。しかし、江戸時代に入ると、木版印刷技術の発達により、多くの書物が比較的安価に製作されるようになりました。
出版文化の始まりは、江戸時代前期(1600年代)の上方(現在の京都・大阪地域)でした。当時は仏教書や実用書が中心でしたが、しだいに物語や娯楽的な内容の本も出版されるようになります。そして江戸時代中期(1700年代)になると、江戸(現在の東京)でも出版業が盛んになり、独自の文化が花開きました。
出版物が広まった背景には、庶民層の識字率向上があります。寺子屋といった教育機関の普及により、商人や町人といった一般の人々も読み書きができるようになりました。これにより読者層が拡大し、彼らの需要に応える形で多様な出版物が生まれたのです。
例えば、今日の小説にあたる「戯作」と呼ばれる娯楽的な読み物や、絵と文章を組み合わせた「絵本」、美しい絵画である「浮世絵」などが人気を集めました。これらは現代の漫画や小説、アートのような役割を持ち、当時の人々の娯楽となっていました。
江戸時代の出版物は単なる娯楽にとどまらず、情報伝達や教育、社会批評の場としても機能していました。現代のインターネットやSNSが果たす役割に近いものがあったと言えるでしょう。
「刊本」と「摺物」
企画展のタイトルにある「刊本」と「摺物」は、いずれも江戸時代の出版物を指す専門用語で、読み方は「かんぽん」と「すりもの」です。これらの言葉について詳しく見ていきましょう。
「刊本」とは、木版印刷で製作された書籍のことです。木の板に文字や絵を彫り、そこにインクを塗って紙に押し付けることで印刷します。今でいう「本」にあたるもので、物語、実用書、教科書など様々な種類がありました。
一方、「摺物」は同じく木版印刷で作られますが、主に一枚物の印刷物を指します。浮世絵はその代表例です。他にも、年賀状のような季節の挨拶状、宣伝のためのチラシ、歌舞伎の番付表(プログラム)なども摺物に含まれます。現代でいえば、ポスターやグリーティングカード、パンフレットのような役割を果たしていました。
両者の違いは、本のように綴じられているか(刊本)、一枚物か(摺物)という点が主な違いです。しかし、制作方法はどちらも木版印刷という同じ技術が使われていました。
例えば、浮世絵師として有名な葛飾北斎や歌川広重の風景画は、美しい摺物として人気を集めました。また、「読本(よみほん)」と呼ばれる娯楽的な物語は、挿絵入りの刊本として多くの読者を獲得しました。
江戸時代の木版印刷技術は非常に高度で、多色刷りも可能でした。「錦絵」と呼ばれる多色刷りの浮世絵は、10色以上もの色を重ねて印刷する精巧な技術が用いられており、当時の西洋人も驚くほどの芸術性を持っていました。
浮世絵―江戸時代のビジュアルメディア
浮世絵は江戸時代に発展した木版画による絵画で、「浮世(うきよ)」、つまり当世風の世相を描いたものです。最初は墨一色の「墨摺り」だけでしたが、技術の発展により多色刷りの「錦絵(にしきえ)」が生まれ、鮮やかな色彩で人々を魅了しました。
浮世絵の題材は多様で、美人画、役者絵、風景画、相撲絵、武者絵など様々なジャンルがありました。現代の写真やポスター、イラストのような役割を果たし、人々の暮らしに彩りを添えていたのです。
歌川広重や葛飾北斎などの浮世絵師の作品は、当時の庶民に人気があっただけでなく、後にヨーロッパの印象派の画家たちにも影響を与えました。日本の伝統文化が世界に広がった例のひとつといえるでしょう。
戯作―江戸時代の娯楽小説
戯作(げさく)は、江戸時代中期から後期にかけて発展した、娯楽のための物語や小説です。「戯れに作る」という意味があり、真面目な学問書や実用書と区別して、楽しみのために書かれた文学作品を指します。
戯作には、恋愛小説の「浮世草子」、笑いを誘う「滑稽本」、恐ろしい話の「読本(よみほん)」など様々な種類がありました。現代の小説やマンガのジャンルの多様さに似ていますね。
山東京伝や曲亭馬琴などの戯作者は、当時の人気作家でした。特に馬琴の『南総里見八犬伝』は、全106冊にも及ぶ大長編で、現代の連載小説やテレビドラマのシリーズのようなものだったと考えられます。
企画展の見どころ
江戸時代の戯作文学と那須の伝説「殺生石」
企画展で紹介されている『絵本三国妖婦伝』や『殺生石後日怪談』は、那須地域に伝わる「殺生石」の伝説を題材にしています。この関係について見ていきましょう。
「殺生石」とは、栃木県那須町にある石のことで、その石に近づくといきものが死んでしまうという伝説がありました。この石の正体は、古来より伝わる「九尾の狐」の変化した姿だとされています。九尾の狐は、中国や日本の伝説に登場する妖怪で、美しい女性に化けて人を惑わすと言われていました。
江戸時代の作家たちは、このような民間伝承や伝説を題材にして物語を創作していました。企画展で紹介されている高井蘭山の『絵本三国妖婦伝』は、日本・中国・インドの三国に伝わる妖婦(妖しい女性)の物語を絵本形式で紹介した作品です。この中で、日本の妖婦として殺生石の九尾の狐が取り上げられています。
また、曲亭馬琴の『殺生石後日怪談』は、九尾の狐の物語をベースにした長編小説です。馬琴は江戸時代後期を代表する作家で、『南総里見八犬伝』などの大作で知られています。彼の作品は複雑な構成と奥深いテーマで人気を集め、当時のベストセラーとなっていました。
このように、那須の殺生石伝説は江戸時代の出版文化において重要な題材の一つとなっていました。地域の伝説が全国に知られる作品となり、また文学作品によって伝説自体も広まるという相互作用があったのです。
江戸時代の出版文化は、地域の伝説や民間伝承を全国に広める役割も果たしていました。これは現代のメディアが地方の観光スポットや文化を紹介するのに似ています。那須の殺生石も、文学作品によって全国に名が知られるようになった例と言えるでしょう。
刊本・摺物で見る江戸の庶民文化
この企画展の最大の見どころは、那須歴史探訪館所蔵の刊本や浮世絵を通して、江戸時代の庶民文化を垣間見ることができる点です。江戸時代は武士だけでなく、町人や商人といった庶民層も文化の担い手となった時代でした。彼らの好みや趣向、日常生活が出版物に反映されています。
例えば、浮世絵には当時の流行のファッションや人気の場所、芝居の場面などが描かれています。また、戯作には、庶民の恋愛や冒険、笑い話などが描かれ、当時の人々の娯楽となっていました。これらの資料は、教科書には載っていない「生きた江戸時代」を感じることができる貴重な資料です。
また、多くの出版物が美しい挿絵や絵画を含んでいる点も注目に値します。活字だけでなく、視覚的な要素も豊かな当時の出版物は、現代のイラスト入り書籍や雑誌、漫画の先駆けとも言えるでしょう。
関連イベント
5月10日には「殺生石の由来と歴史的背景」をテーマにした講座が開催されます。元那須歴史探訪館館長の齊藤宏壽氏による講演で、殺生石伝説の歴史的背景について詳しく学ぶことができます。
「生誕150周年 山田英夫~会津・長州・那須を繋ぐ~」というトピック展も見逃せません。会津藩主・松平容保の三男として生まれながら、幕末の対立軸にあった長州藩出身の山田顕義の娘と結婚し、山田家の家督を継いだ山田英夫の生涯は、まさに日本の近代化を体現するものでした。
彼が那須地域で取り組んだ黒田原駅前の新市街地設定や山田農場の経営は、地域の近代化に大きく貢献しました。この展示からは、全国的な歴史の流れと地域の発展がどのようにつながっていたかを読み取ることができるでしょう。
幕末から明治にかけての激動期に、かつての敵対勢力(会津と長州)の血を引く人物が結ばれ、新しい時代の地域発展に尽力した歴史は、単なる地域史を超えた魅力があります。
まとめ:江戸の出版文化と那須の歴史が交わる貴重な機会
江戸時代の出版文化は、現代のインターネットやSNSの普及に例えられるような「情報革命」でした。識字率の向上と出版技術の発展により、それまでエリートだけのものだった「読む」という行為が庶民にも広がり、多様な娯楽作品が生まれました。
那須歴史探訪館の企画展「刊本・摺物ワンダーランド」は、そんな江戸時代の出版文化を実際の資料を通して体感できる貴重な機会です。特に那須地域ゆかりの「殺生石」伝説を題材にした作品は、地域の歴史と全国的な文学文化の関係を知る上で見逃せません。
2025年3月28日から6月29日まで開催される本展示を通じて、私たちの先祖がどのように情報や文化を享受していたのか、ぜひその一端に触れてみてください。
- 江戸時代の出版文化が那須の歴史と交わる企画展
- 期間は令和7年3月28日~6月29日
- 江戸時代は木版印刷技術の発達で出版が拡大
- 「刊本」は書籍、「摺物」は一枚物の印刷物
- 那須の「殺生石」伝説が文学作品に
- 九尾の狐物語の人気を感じられる展示
- 江戸時代は庶民も文化の担い手に
- 山田英夫は会津と長州をつなぐ人物
- 那須地域の近代化に貢献した足跡
- 那須歴史探訪館は独特の建物デザイン
- 5月10日に「殺生石」講座も開催
- 古文書の閲覧も可能な貴重な機会

