東洋経済オンラインの記事によると、2025年春の東大理3合格者30名のうち8割以上が生成AIを学習に活用していることが明らかになりました。従来「答えを教えてもらう道具」として使われがちな生成AIを、これらの合格者は「自分の力で解けるように導く道具」として活用していました。問題出題・音声解説・英作文添削という3つの手法を軸に、AIが学習を深める実践的なパートナーとして機能している実態が浮き彫りになっています。
- 段階的な難易度調整がポイント
- 答えではなくヒントを求める思考法
- RAGとLLM
- RAG技術が実現する「ハルシネーション」の抑制
- Gemini 1.5 Proが支える音声生成技術
- AIによる添削精度の現在地
- AI添削の技術的限界と適切な活用法
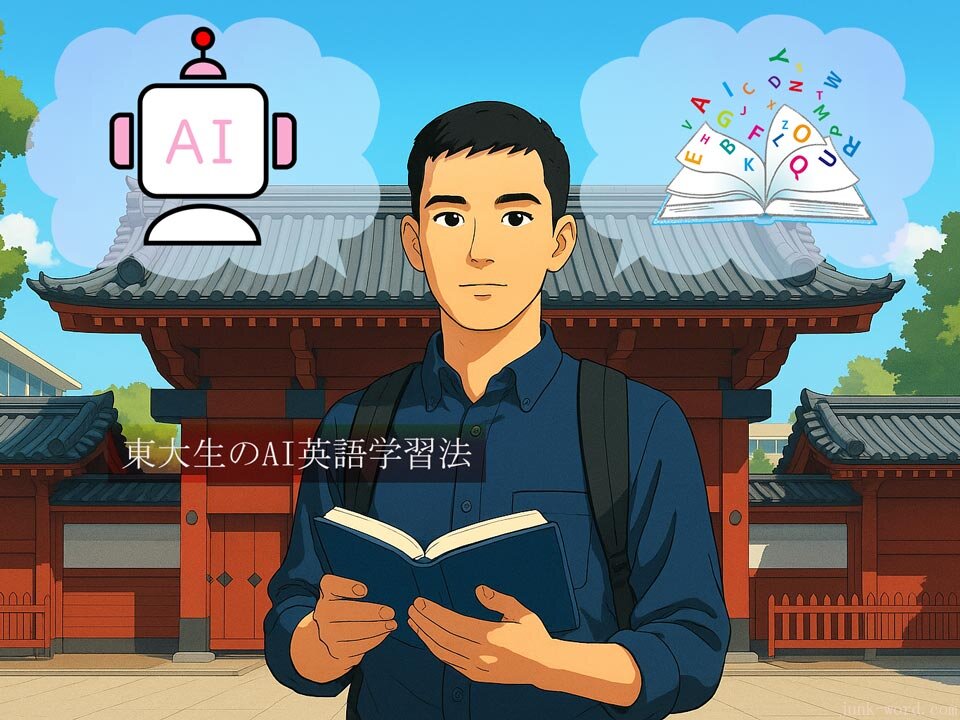
段階的な難易度調整がポイント
東大理3合格者が実践していた第1の手法は、生成AIに問題を出題してもらうことです。この手法では、まず自分の学年と出題範囲を明確に伝えることから始まります。「自分は中学3年生です。今度学校のテストで二次方程式の文章題が出る予定です。中学3年生の範囲の文章題の問題で、難しすぎないレベルのものを3問出題してください」といった具体的な依頼を行います。
重要なのは、一度の依頼で理想的な問題が出るとは限らないことを理解し、対話を重ねながら調整していくことです。「3問目のレベル感がちょうどよかったので、類題をもう3問出してください」「もう少し難易度を上げてください」といったやりとりを通じて、自分に最適な難易度の問題を作り上げていきます。
中には「過去10年分の東大の英作文の問題」を読み込ませ、「この問題の類題として今年出題される可能性のある問題を出してください」という高度な活用をしていた合格者もいました。このように、AIとの対話を通じて自分だけの問題集を作成する手法が、多くの合格者に共通して見られました。
答えではなくヒントを求める思考法
この手法で最も重要なのは、答えや解説をすぐには求めないことです。問題が解けなかった場合には「難しいので、ヒントをください」と依頼し、段階的なヒントを受け取りながら自分の思考を前に進めていきます。自分で考える力を維持しながら、行き詰まりを解消することができます。
答えをすぐに見てしまう使い方では、自分で考える力は身に付きません。AIから適切なヒントを得ながら、最終的には自分の力で答えに辿り着くプロセスこそが、真の学習効果を生み出します。この点が、東大合格者のAI活用法における最も重要な特徴と言えるでしょう。
問題の難易度調整は一回では完成しません。「このレベルがちょうど良い」「もう少し易しく」といった対話を重ねることで、自分に最適な学習環境を作り上げることができます。このカスタマイズ機能こそが、AIを活用した学習の大きな利点です。
NotebookLMが切り拓く「AIリサーチアシスタント」の世界
東大合格者が活用したNotebookLMは、ユーザーがアップロードした資料や情報に基づいて回答できるなど、近年普及が進んでいるRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を活用したAIサービスの一つです
RAGとLLM
AI技術の進化が著しい近年、「RAG」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これは、従来のLLM(大規模言語モデル)の弱点を補い、より信頼性の高い情報を生成するために登場した重要な技術です。
RAGとLLMは密接に関係していますが、それぞれのアプローチには大きな違いがあります。
まずLLMは、インターネット上の膨大なテキストデータをもとに学習し、人間のように自然な文章を生成する能力を持っています。しかし、その知識は学習時点でのものであり、常に最新の情報にアクセスできるわけではありません。また、学習データに含まれるバイアスや誤情報をそのまま反映してしまうこともあります。
さらに問題とされているのが、「ハルシネーション(事実に基づかない生成)」と呼ばれる現象です。これは、文脈に関係のない内容や事実と異なる情報を、あたかも本当のようにもっともらしく生成してしまうことを指します。こうした課題を解決するために登場したのがRAGです。
RAGは、ユーザーの質問や指示に応じて、まず外部の情報源(データベース、ドキュメント、ウェブサイトなど)から関連情報を「検索(Retrieval)」し、その検索結果に基づいてLLMが文章を「生成(Generation)」するという仕組みになっています。
RAG技術が実現する「ハルシネーション」の抑制
RAGは、生成AIが外部の情報源やユーザーの提供した資料を参照しながら回答を作成できる仕組みです。この技術により、AIが自らの学習データのみに頼って回答を生成する場合に起こりがちな「ハルシネーション」を、ある程度抑えることが可能になりました。
たとえば、Googleの「NotebookLM」では、ユーザーがアップロードした資料を中心に参照して回答が生成されるため、「どの文書に基づいているのか」「出典が示されているか」が比較的明確になりやすいという特長があります。これにより、回答の信頼性を確認しやすくなると同時に、ユーザー自身が根拠を検証することも容易になります。
とはいえ、資料に書かれていない内容について尋ねたり、曖昧な質問をした場合には、AIが不完全な情報を補おうとして誤った回答を生成してしまうリスクも依然として存在します。そのため、RAGを活用する際でも、ユーザーが回答の根拠を慎重にチェックする姿勢は欠かせません。
また、ChatGPTやClaudeといった他の主要な生成AIでも、RAG技術を活用した機能が続々と導入されています。ウェブ検索結果を引用したり、ユーザーのアップロード資料に基づいて回答を行ったりと、信頼性を高める工夫が進められています。
こうしたツールを使いこなすためには、それぞれのAIがどのように情報を参照し、どのように引用を表示するのかといった仕様を理解しておくことが大切です。「出典が明示されているか」「参照元と回答に矛盾がないか」を確認する習慣が、ハルシネーションを避け、信頼性の高い情報を得るための鍵となるでしょう。
Gemini 1.5 Proが支える音声生成技術
NotebookLMの音声概要機能には、GoogleのGemini 1.5 Proという最新の大規模言語モデルが使用されています。このモデルは公開ベンチマークでも上位の日本語処理性能を示しており、音声概要機能は2024年に導入され、2025年4月には日本語を含む50以上の言語に対応しました。
NotebookLMでは、資料をアップロードすると要約や情報抽出が可能となり、場合によっては対話形式の出力にも対応しています。資料のポイントを分かりやすく提示することで、復習や移動中の学習など多様な活用が期待されています。
実際の使用例として、教科書や授業のスライド、配布プリントをアップロードすると、AIがそれらを読み込んで要点要約や解説を生成します。「テスト範囲を簡単に説明して」と依頼すれば授業内容のサマリーが得られ、文章を読むだけでは頭に入りにくい内容も、音声として聞くことで理解が深まります。電車での移動中など、テキストを開けない環境でも復習を続けることができるため、学習時間の有効活用にもつながります。
NotebookLMは「Project Tailwind」として発表された後、GoogleのAIプロダクトとして展開されています。学習や業務資料の分析など、幅広い用途が想定されています。
生成AI英作文添削の技術的進歩と限界
英作文添削における生成AIの能力は、今や人間の教師に匹敵するレベルに達しつつあります。しかし、活用する上では押さえておきたいポイントや注意点もあります。
AIによる添削精度の現在地
東大合格者の多くが「英作文添削は先生だけでなく生成AIにも頼んでいた」と答える背景には、AIの添削精度の飛躍的向上があります。現在のChatGPTやGeminiなどの生成AIは、膨大な英語テキストデータで訓練されており、文法の誤り検出から語彙の適切性、文章の自然さまで幅広くカバーできます。
中でも優れている点として、AIが「なぜその修正が必要なのか」という理由も併せて説明できることです。人間の教師の場合、時間的制約から詳細な説明が困難な場合もありますが、AIなら何度でも質問に答えてくれます。東大合格者の事例でも、受験直前期に「最終確認リストを作ってください」という依頼で自分のミスパターンを体系化していたことが分かります。
AI添削の技術的限界と適切な活用法
一方で、AI添削には限界も存在します。AIは統計的な言語パターンに基づいて判断するため、文脈やニュアンスを完全に理解できるわけではありません。また、文化的背景や創造性を要する表現については、人間の判断に劣る場合があります。
教育専門家は「AIの添削結果はあくまで参考レベル」として、重要な文書では専門家による二重チェックを推奨しています。しかし、学習ツールとしては「その場で即時に添削結果が返ってくるスピード」「24時間いつでも利用可能」「何度でも質問できる」といったメリットが、学習効率の大幅な向上を実現しています。
東大合格者の成功例が示すように、AIを「完璧な教師」として依存するのではなく、「学習を加速させる強力なツール」として適切に活用することが重要です。これにより、従来の学習方法では実現困難だった高頻度・高密度の練習が可能になり、英語力の飛躍的向上につながるのです。
一部の英語学習AIツールでは、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づくレベル判定機能も提供されています。これにより学習者は自分の現在の英語レベルを客観的に把握し、目標に向けた学習計画を立てることができます。AIの多角的活用が、個別最適化された英語学習を実現しています。
東大生のAI英語学習法のまとめ
- 東大理3合格者30名の8割以上が生成AIを学習に活用
- 問題出題では対話を重ねて難易度を最適化
- 答えではなくヒントを求めて思考力を維持
- RAG技術で外部情報を参照し信頼性を向上
- NotebookLMはアップロード資料に基づく回答で出典明示
- ハルシネーション抑制には出典確認が重要
- Gemini 1.5 Proが音声概要機能を支える
- 2025年4月に50以上の言語に対応
- 移動中でも音声で復習可能
- AI英作文添削は即時フィードバックが可能
- 修正理由の説明でミスパターンを分析
- AI添削は参考レベルとして活用が適切
- AIを「考える力を養う道具」として活用することが成功の鍵


