MITの研究チームが54人の参加者を対象に、ChatGPTを使ったエッセイ執筆が脳活動に与える影響を調査しました。脳波測定の結果、ChatGPT使用者は最も低い脳の活動性を示し、記憶力も低下していることが判明しました。しかし、研究責任者は「脳が腐る」といった表現は適切ではないと慎重な姿勢を示しています。この研究は生成AI時代における人間の認知機能への影響を探る重要な第一歩となっています。
- 脳波測定でわかった脳内ネットワーク
- 神経接続性が示す「考える力」の違い
- なぜエッセイが思考力を鍛えるのか
- 「書くことは考えること」の科学的根拠
- よくある質問
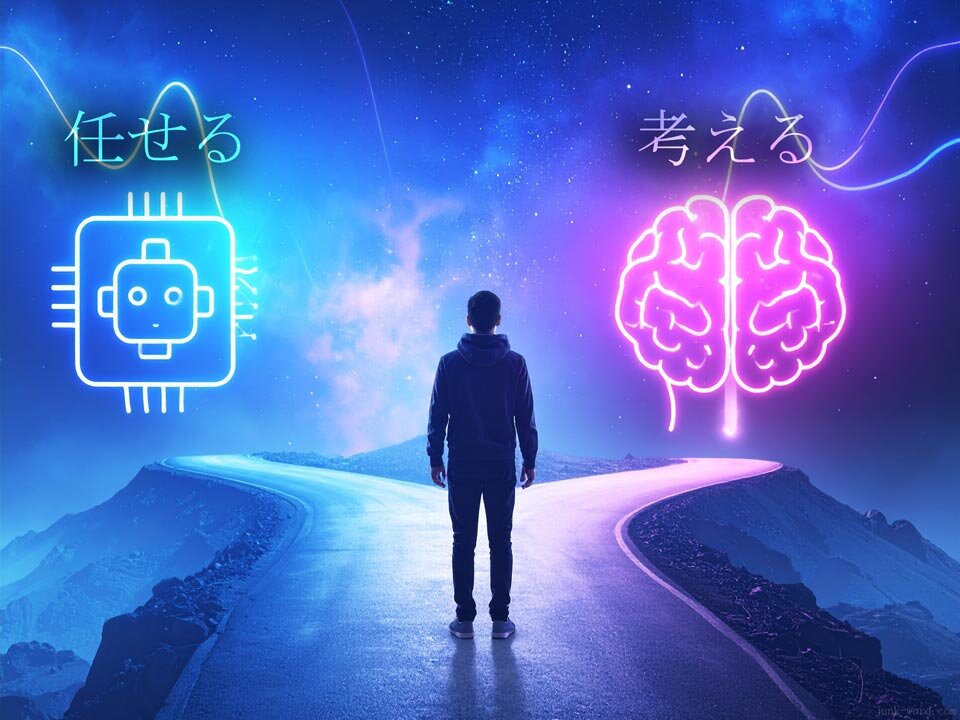
脳波で見える思考活動の実態
脳波測定でわかった脳内ネットワーク
脳波検査は通常、医療現場でてんかんの診断、意識障害の評価、頭部外傷後の脳機能確認、睡眠障害の診断などに使用されています。頭皮に電極を装着するだけの安全で非侵襲的な検査で、脳が正常に活動しているか、異常な電気活動が起きていないかをリアルタイムで監視することができます。脳波は年齢や意識レベルによって変化し、医師は同年代の平均的な波形と比較することで、脳の健康状態を評価します。
脳波(EEG)は、脳神経細胞の電位変化を捉える計測法で、主な周波数帯は0.5〜30Hz、振幅は数十マイクロボルト程度(通常10〜100 μV)です。計算問題などに集中するとアルファ波(8-13 Hz)が減少し、ベータ波(14 Hz以上)が優勢になることが知られています。
今回のMIT研究では、この医療技術を認知科学研究に応用し、エッセイ執筆中の脳活動をリアルタイムで観察しました。研究者たちは参加者の頭部に電極を装着し、エッセイを書いている最中の脳内ネットワークの活動パターンを詳細に分析したのです。これにより、従来は見えなかった「思考プロセス」を客観的に測定することが可能になりました。
神経接続性が示す「考える力」の違い
脳波測定により、脳だけで書いた参加者は最も強く分散したネットワークを示し、検索エンジン使用者は中程度の活動、ChatGPT使用者は最も弱い接続性を示しました。これは、脳の各領域がどれだけ協調して働いているかを示す重要な指標です。
最初に脳だけでエッセイを書いていた人は、その後ChatGPTを使った場合でも比較的高い脳活動を示しました。一方、最初からChatGPTに頼っていた参加者は、ツールを使わない状況でも脳の働きが弱まっていました。これは、思考習慣が脳の活動パターンに影響を与える可能性を示唆しています。
脳の可塑性を示す例として、九州大学の研究では、わずか3日間の脳波訓練により長期記憶能力が向上できることが示されています。これは訓練によって脳機能を改善できる能力を示しており、適切な方法で思考力を鍛えれば脳の働きを向上させることができる可能性があります。
エッセイが育む思考力の価値
エッセイ執筆は文章練習というだけでなく、自分の思考を深め、世界を理解する重要な学習プロセスです
なぜエッセイが思考力を鍛えるのか
エッセイとは、自分の体験や知識、考えをもとに、なぜそう考えたのか、どんな背景があるのかを掘り下げて表現する文章形式です。「楽しい」「良かった」で終わらず、そう感じるに至った心の動きや背景等を掘り下げることが大切です。体験や感想を綴るという点で作文と似ていますが、読者が共感する事柄を織り交ぜ、より深い内省を要求するのがエッセイの特徴です。
文章を書く過程では、自分の体験を振り返り、感情の動きを分析し、読者に伝わりやすい表現を考える必要があります。この一連のプロセスが、脳の多様な領域を活性化させ、思考力の向上につながると考えられています。
「書くことは考えること」の科学的根拠
MIT研究では、エッセイ執筆中の脳活動を詳細に分析することで、「書く」という行為が文字の羅列ではなく、複雑な認知プロセスであることが科学的に証明されました。脳波測定の結果、自分だけで書いた参加者は、脳の前頭葉と頭頂葉の間で活発な神経接続を示し、これは高次の思考や記憶処理に関連する重要な活動パターンです。
特に注目すべきは、アルファ波とベータ波といった周波数帯で明確な差が確認された点です。これらの帯域は創造的思考や記憶処理と関連するとされますが、ChatGPT使用者では活動が相対的に低減していました。
ミシシッピ大学の研究者が「書き始めるときは自分が知っていることからスタートしますが、書く行為を通じて次に問うべきことや新しいアイデアが見えてくる」と述べているように、執筆プロセスは既存の知識を整理し、新たな洞察を生み出す認知的な作業なのです。脳科学的に見ると、この過程では記憶の検索、情報の統合、論理的な構成といった複数の脳機能が同時に働いています。
研究結果によると、自分だけで書いたグループは「表現が個性的で、まさに『自分の言葉』で文章を書いていた」のに対し、生成AI使用グループのエッセイは「互いによく似ていて、画一的な傾向が目立った」とされています。これは脳波データと一致しており、AI依存が創造性や個性的思考を司る脳領域の活動を阻害していることを示唆しています。さらに、ChatGPT使用者は執筆直後に自分が書いた内容を思い出せない傾向が強く、記憶の形成プロセスも阻害されていることが明らかになりました。
エッセイ執筆は現代のSNSやブログでの情報発信とは異なり、深い内省と論理的思考を要求します。自分の体験や感情を感じるまでの心の動きや背景を掘り下げて文章で表現する過程が、脳の神経接続性を強化し、記憶の定着を促進する可能性があります。
よくある質問
この研究の信頼性はどの程度でしょうか?
この研究は現時点では査読前のプレプリント段階です。研究者も制限事項を明確に示しており、参加者が54人と比較的少数であることや、長期的な影響についてはさらなる調査が必要であることを認めています。ただし、脳波測定という客観的な手法を用いており、初期の科学的証拠として価値があります。今後、より大規模で多様な研究による検証が期待されています。
既にChatGPTを頻繁に使っている場合、脳への悪影響は取り返しがつかないのでしょうか?
心配する必要はありません。脳には「可塑性」という素晴らしい能力があり、新しい習慣によって神経接続を改善できます。脳の可塑性を示す研究例では、適切な訓練で脳機能が向上することが示されています。まずは短時間でも「自分だけで考える時間」を意識的に作り、段階的にAIに頼らない思考習慣を増やしていくことが効果的です。
ChatGPTと検索エンジンの脳への影響に差があるのはなぜですか?
検索エンジンでは「情報を探し、選別し、組み立てる」という思考プロセスが必要ですが、ChatGPTでは完成された回答をそのまま受け取るため、脳の活動量に大きな差が生まれます。検索エンジン使用時は複数の情報源を比較検討する必要があるため、脳の多様な領域が活性化されるのです。これが、MIT研究で検索グループが中程度の脳活動を示した理由です。
子どもがChatGPTを学習に使うのは危険でしょうか?
完全に禁止する必要はありませんが、使い方が重要です。まず自分で考え、調べ、書いてみる経験を十分に積んでから、補助ツールとしてAIを活用するのが理想的です。研究で示されたように、最初に自力で取り組んだ人はAI使用時も高い脳活動を維持できました。「考える力」をしっかり育ててからAIと付き合うことで、両方の利点を活かせます。
エッセイ以外でも同様の効果は期待できますか?
はい、「自分で考え、整理し、表現する」プロセスがあれば同様の効果が期待できます。日記、読書感想、議論への参加、問題解決の際に「なぜ?」「どうすれば?」と自問する習慣などが効果的です。重要なのは、与えられた答えをそのまま受け入れるのではなく、自分の頭で咀嚼し、自分の言葉で表現することです。MIT研究でも今後は他の活動への影響を調べる予定とされています。
脳波測定は誰でも受けられるのでしょうか?
脳波検査は多くの医療機関で実施されており、身体的負担が極めて少ない安全な検査です。頭皮に電極を装着するだけで、痛みを感じることはほとんどありません。ただし、今回の研究のような詳細な認知機能分析は研究機関でのみ行われています。一般的な脳波検査はてんかんや睡眠障害の診断に使われ、年齢を問わず受けることができます。
ChatGPTの使用と脳の活動・まとめ
- MIT研究は査読前のプレプリント段階
- 54人を対象にChatGPT使用時の脳活動を測定
- ChatGPT使用者は最も低い脳の活動性を示した
- 脳波測定で神経接続性の違いが明確に可視化
- 記憶力と自己モニタリング能力の低下が確認
- 「脳が腐る」は科学的に正確ではない表現
- 脳波は微細な電気信号から思考状態を解析
- エッセイ執筆は思考力を鍛える重要なプロセス
- 最初に自力で学習した人はAI使用時も高い脳活動を維持
- AI依存は創造性や個性的思考を阻害する可能性
- 脳の可塑性により適切な訓練で機能向上は可能

